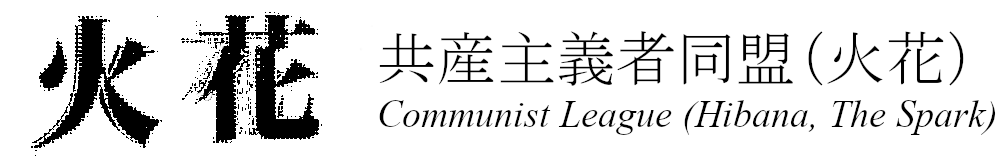「国民国家」の謎
斎藤 隆雄
470号(2025年03月)所収
今回は「国民国家」の謎について集中的に論じたいと思う。いわゆる従来の「国家論」という切り口ではなく、近代における国民統合の意味と国家というまとまりの中にある社会活動が帯びる特異な傾向を考えてみたい。そして、これまで私が感じていた、戦後の第三世界における民族独立とその結果による国民国家形成の異質性についても触れたい。
■ これまでの議論
467号で発表した論文では、国民国家を巡る二つの大きなうねりがあると見てきた。一つは近世近代に欧州で始まる「国民国家」樹立のうねりであり、もう一つはその欧州国民国家の帝国主義国家への変容とその侵略が生み出した植民地国家における「国民国家」樹立への願望を含めたうねりである。この二つの世界史的レベルでの近世近代における領域政治あるいは領域支配の構造はこれまで世界システム論という形で論じられてきた課題である。ウォーラーステインのそれが有名であるが、このシステムの議論の前提となっているのが資本主義の世界的拡大とそれに伴う領域政治の形態あるいは経済的社会的形態を類型化するということだった。中心、周辺、亜周辺という三つの形態がそれである。
このシステム論は「システム」という限りにおいて現状の世界資本主義体制を全体として世界分業という観点から固定的に捉えられるという限界が見られる。資本主義の世界的拡大発展という単線的な歴史を前提としつつも、資本主義が周辺を必要とするという意味では従来の単純な発展史観とは異なって、見方によれば植民地支配構造そのものが資本主義経済にとって必要不可欠なものとして前提されているようにも見える。その点が、世界システム論が欧米中心主義だと批判される所以であろう。私はこのような観点からシステム論が人類の主体的な行動を捨象し、欧米支配の固定化を正当化するブルジョアジーの称揚する理論であると考える。ただし、彼の理論が明らかにした「資本主義は周辺を必要とする」という発見は注目に値する。何故なら、もしそうであるなら、世界が有限である限り資本主義はその周辺との角逐のなかで衰退もしくは破綻するというシナリオもまた可能だからである。なぜなら、従来の資本主義経済の同心円的拡大を前提するなら、発展すればするほど周辺部分が少なくなり、ついには周辺が存在できなくなってしまえば、資本主義経済それ自体が成立しなくなることになるからである*1。
先述した二つのうねりもまた、同じ「国民国家」を形成する世界政治であるとするなら、植民地国家における「国民国家」形成の動きはそれぞれの国家の国民経済の発展を追求する以上、自明の理としてかつて周辺であった諸国の資本主義的発展はすなわち周辺の反逆という意味合いを持っていると言える。戦後の新植民地諸国の「国民国家」への願望は自らの周辺資本主義的抑圧からの脱出を試みる一つの希求として世界的なうねりとなって現在的に起こりつつあることは周知であろう*2。1980年代以降の第三世界における急速な発展は現在、BRICS諸国等における相対的な勃興における欧米資本主義諸国との均衡体制を形成しつつあることで、世界政治における変動を予感させるものである。
では、そこにおける「国民国家」形成が近世近代の欧州におけるそれとどれほどに相似しているのかということが次に疑問として提起される。果たして、これらの勃興しつつある旧第三世界の資本主義的発展が欧州資本主義的発展過程を踏襲するのか否かということが厳しく問われることとなる。欧州資本主義における国家の発展過程が「いわゆる典型的なもの」であると捉えるならば、勃興しつつある第三世界の発展は周辺を求めて帝国主義的なものとなるのか、それとも非典型的なものとなるのか、あるいは新たな歴史的幕開けであるのかと問いかけているからである。この問いに対して、現在のヘゲモニー国家である米帝国主義の世界政治戦略はとりわけ中国資本主義の帝国主義への発展を予定しつつ、その封じ込め戦略として設定されていることは大方の人々の了解することであろう*3。では、これらの発展過程の行先を分析するために注目すべき事象とは何なのか、と問われれば、当然にも現在闘われている地域戦争であるウクライナとイスラエルにおける地域戦争であることは論を待たないであろう。まさに、これらの戦争の意味するものこそ、これからの世界政治の未来を規定する新たな局面を著していると考えられるのだ。
■ 戦争が生み出す新たな時代とは何か?
日本が日露戦争に勝利して、新たな帝国主義として国民国家を完成させたという歴史過程において、その対極に生まれたのがロシアにおける労働者農民の反乱であった。1905年のロシア革命においてレーニンが提起した新しい革命戦略は言わずと知れた「労農同盟論」であった。この路線は20世紀を通じて革命理論の中心的な役割を果たしたということには異論はないであろう。1960年代における日本の「新左翼」運動の理論的な中心軸が「世界革命」であったということと、この「労農同盟論」とは密接な関わりがある。何故なら、このレーニンが提起した戦略は20世紀の世界革命における歴史的骨子を措定したからである。つまり、この戦略の前提となる国家の歴史過程を次のように規定したからである。
「『ツァーリズムに対する決定的勝利』は、プロレタリアートと農民の革命的・民主主義的独裁である。…そして、このような勝利は、まさしく独裁になる。…それは、どうしても独裁でなければならない。なぜなら、プロレタリアートと農民にとってただちに、ぜひとも必要とされる改革の実現は、地主と大ブルジョアジーとツァーリズムとの死物ぐるいの抵抗をよびおこすからである。独裁なしには、この抵抗をうちやぶることも、反革命的企図を撃退することもできない。しかし、それは、もちろん社会主義的独裁ではなく民主主義的独裁であろう。それはうまくゆけば、農民の利益になるように土地財産の再分配をやり、徹底的な完全な民主主義を実行して共和国を打ち立て、農村生活だけでなく工場生活からもアジア的・奴隷的なものを根こそぎにして、労働者の状態の著しい改善と生活水準の向上の礎を置き、最後に、革命の火事をヨーロッパに飛び火させることができるだろう。」(『民主主義革命における社会民主党の二つの戦術』p.60国民文庫)
「マルクス主義者は、ロシア革命のブルジョア的性格を無条件に確信している。これは何を意味するか?それは、ロシアにとって必然なものとなった政治制度の民主主義的改革と社会経済上の改革が、それ自体としては、資本主義をほりくずし、ブルジョアジーの支配をほりくずすことを意味しないばかりでなく、逆に、資本主義の幅の広い急速な発展、アジア的でないヨーロッパ的な発展のための地盤をはじめてはききよめ、階級としてのブルジョアジーの支配をはじめて可能にすることを意味している。」(同48)
これは有名な「二段階革命論」としてのちにスターリンが定式化した革命戦略論であるが、ここで論じられている「ブルジョア革命」とは封建的農奴制の下にある国家(帝国)に対する民主的共和制国家すなわち「ブルジョア国民国家」の形成主体がブルジョアジーであるということを明確にさせるための議論である。このことは実は同時期のトロツキーの世界革命論との対比で違いが浮かび上がる。トロツキーは05年革命の総括文書『結果と展望』において、労農政府ではなく、労働者政府を対置し、ヘゲモニーと見通し一般を語った。この視点の重要性に気付いたのは、60年代日本の新左翼活動家である八木沢氏である。
彼は「二つの戦術」を巡る議論について次のように論じている。
「レーニンは、見通し一般を問題にしたのではなかった。革命がブルジョア民主主義革命であるという分析に立って、だが、その革命の過程を通じて、どのようなヘゲモニーと闘争するのか、その闘争いかんが、次のプロレタリアートの地歩を決定するという事であった。…マルクスの永続革命論は、トロツキーの永続革命論へではなくレーニン『二つの戦術』へと継承されたのである。」(八木沢『反スタ主義の止揚と現代革命』)
ここで言うところのマルクスの永続革命論は1848年革命の総括である「共産主義者同盟中央委員会の呼びかけ」に書かれたものであるが、この時代のプロレタリアートのヘゲモニーは明らかに時代的限界性を抱えていたことは確かであり、1905年における帝国主義段階におけるそれとは異なっている。レーニンはそれを次のように語っている。
「ブルジョア民主主義的秩序には、ドイツのようなものもあれば、イギリスのようなものもあり、オーストラリアのようなものもあれば、アメリカまたはスイスのようなものもある。だから、民主主義的改革の時代に、民主主義のいろいろな段階の間の差異と、民主主義のあれこれの形態の違った性格の間の差異を」見極め、「この枠を大いに押し広げることができる」(『二つの戦術』p.52)と。
つまり、48年から半世紀後の帝政ロシアにおける戦略は民主主義的改革の時代として捉え、封建農奴制から資本主義制へと国家統治形態の変革の時代が到来しているとしているのである。この路線は第二次世界大戦末期まで続き、毛沢東の新民主主義論へと連なることとなる。17年ロシア革命後の国家建設におけるスターリンの路線がこのレーニンの世界史的理解からは導き出されないということは明らかであるが、それはここでは問わない。むしろ、その後の1930年代における世界革命情勢を巡る論戦については、日本のブントは「スタ・ブハ綱領」批判とドイツ・フランス革命の敗北として総括しており、唯一光明を切り開いたのが中国における「民族解放闘争」であったとするのである。
「第一次大戦とロシア革命とによってこの植民地のブルジョアジーと帝国主義ブルジョアジーに一定の『癒着』が開始され、植民地解放闘争はレーニンが述べた如く、ブルジョア民主主義というより「民族革命」的とよばれるにふさわしいものとなったのである。」(八木沢)
このブルジョア民主主義革命から民族解放闘争への視点の転換は現実がそうであるということ以上に大きなものである。というのも、30年代から戦後にかけて世界的に拡大した「民族解放闘争」に対して、かのスターリンは二段階革命論に基づきながら、情勢に強制されるまで民主主義革命にこだわったからである。例えば、中国革命において毛沢東が内戦で勝利するまでスターリンは蒋介石の肩を持っていたことは有名である。これは逆に言えば、スターリン主義批判として民族解放闘争を評価するという効果も発揮したのであるが、世界史的な観点から見るならば、中国革命が民主主義革命であることは疑いようのない事実でもある。問題はスターリンが中国共産党の民主主義革命におけるレーニン的ヘゲモニー*4を理解できなかったということなのだろう。つまりこのことこそ、ロシア革命における民主主義革命の未完という側面を鋭く照射するのである。スターリンの犯した最大の間違いはレーニン死後のソビエト共和国における民主主義革命を最後まで完遂することなく国家社会主義体制としてモザイク的に打ち固めてしまったことなのである。そのことが百年後にウクライナにおけるロシアに対する独立戦争として立ち現れてきた所以でもあるのだ。まさに、レーニンが言った「アジア的でないヨーロッパ的な発展」が今もまだロシアにおいては成就していないということこそ根底的な根拠であるだろう*5。つまり、レーニンが提起した「労農同盟」政府がブルジョア独裁として民主主義革命を完遂するというイレギュラーな革命戦略の特異な形態こそ問題の本質を照らし出しているのである。
■ 資本主義は周辺を必要とするか
現在のEUはかつてヒトラーが武力で成し遂げようとしたことを経済で実現させた、と誰かが語っていたが、それを言うなら、ナポレオン・ボナパルトもそうだし、ローマ教会もそうだと言えるだろう。これは欧州諸国における「国民国家」を分析する上での一つのヒントであるように思われる。まず疑問として浮かび上がるものが、「何故、ポーランドとウクライナの間に溝があるのか」、「何故、ボスポラス海峡が分岐線なのか」という問題である。これはもちろん、ローマ帝国とキリスト教(カソリックと新教)の領域だからであると答えることができる。そしてこの領域の国民国家は再び帝国領域で連合し始めているのである。つまり、国民国家という統治形態は欧州においては過渡的な形態であり、再びローマ帝国領域へと統合しつつある、と。
では何故、国民国家が再び連合せざるを得なかったのか。国境の自由通行と関税の廃止は逆に言えば、本来資本主義経済においては最も基本的な要求だったはずである。かつて都市国家と領主支配の封建制においては細分化された諸国家のモザイク状態が常態であったが、16世紀以降の欧州経済の資本主義的発展において言語、宗教、慣習の共通性を基礎にしつつ漸次統合されていったというのが国民国家の当初の形態であった。これは何も平和的に統合されていったのではない。ブルボン朝、プロイセン、チューダー/ステュアート朝などの諸王朝は戦争無くして統合はありえなかった。その意味では日本の近世幕末期における幕藩体制の解体もまた戦争によって統合された*6のであって、自然発生的に生まれたのではなかった。この統合はまた同時に領土というだけではなく、階級という意味においても戦争だった。領域と階級の間の熾烈な競合と策謀と戦争によって漸次的に統合されていったのが国民国家であったのだ。そしてその資本と統治の統合の過程で突き当たったのが国民統合という壁であったのだ。当初、元々細分化されていた生活世界の小さな領域を領主なり国王なりが統治するには大きな領域統治は困難だった。交通手段が未発達な時代では直接的な統治には限界があったと考えるのが自然だろう。帝国統治は間接的な統治だから、領域を確定するには文化的な資源(世界イデオロギー)が必要だったが、直接的統治はそうではない。それがある程度広がり得たのは戦争による収奪経済のおかげであった。中世紀の国家形成がその典型であろう。江戸期の幕藩体制が間接統治であった根拠は徴税体制の分権である。政治的な日本国の統治体制は征夷大将軍である徳川家によって統合されていたとしても、各藩の統治は独立していたと考えていいだろう。これを近代国民国家として衣替えするには中世紀における戦争とは桁違いの人員を必要とされた。欧州におけるナポレオン戦争がそうであり、日本における戊辰戦争がそうであるように、国民国家側の近代的兵器とともに徴兵による総動員体制が必要となる。
ナポレオンがローマ帝国領域を自らの領域として派兵していったのは、ある意味では自然な行動だったと思われる*7。ナポレオンの失敗はかのモスクワでの敗退だったというのが常識的な見解かもしれないが、本質的にはむしろ敗北の原因は英国資本主義との格差であったと思われる。つまり、大陸諸国の資本主義発展の段階とヘゲモニー国であった英国資本主義の発展の段階との格差が彼我の周辺領域の領有の差であった訳で、競争力の源泉が植民地収奪であったということは、この産業資本主義段階における資本主義経済が周辺を必須としたことの証左でもある。そして、ウォーラーステインのシステム論が言うようにこの国民国家戦争による亜周辺における資本主義的覚醒と国民統合の統治形態の輸出が逆に資本主義経済の単純な拡大を許さなかった根拠でもある。資本主義の無国籍的拡大指向に対する一旦の歯止めが国民国家であったのだ。
しかし、この歯止めが20世紀後半になって欧州において逆回転し始めたのは何故か。そこには二つの根拠があると考えられる。一つは資本のグローバリゼーションがソビエト連邦国家という帝国を解体したことと、もう一つは植民地・半植民地諸国の政治的独立による資本主義にとっての周辺経済圏の変質である。この二つの現実に対する欧州資本主義の反応は縮小版世界経済の形成である。独仏を中心国家としてかつてのローマ帝国圏という文化的同一性を梃子に囲い込みを始めたと見るのが妥当であろう。国民国家形態というのは、先にも指摘したように国民という均質化された労働者階級を形成することに主眼があるのであって、この人間的契機、労働者として兵士として納税者として均質な人間的流動性を確実なものとすることが眼目であり、そのことが他方で資本の壁を形成するということの根拠でもあるだから、この壁の拡張は資本文化の高度なコミュニケーション革命があり、機械化された軍事組織連合の形成があり、WTO等の国際経済法体系があって初めて可能であったと言える。NATOの結成と欧州連合の成長とが密接に結合しているのはそういう根拠として語り得るのだ。
しかし他方でEU圏外からの大量の難民の流入によって本来想定されていた東欧諸国の労働力需要を凌駕することになるという想定外の現実に突き当たって、現状の欧州国内政治は岐路にさしかかっていることは誰の目にも明らかだろう。ただ、これらの政治的説明現実とは裏腹に経済的現実においては移民労働者に依存する欧州経済という経済説明現実もまた存在する。これは資本の高度構成による第三次産業の肥大化がこれらの労働力を領域経済の下層を下支えする役割を果たしているという現実を見なければならない。つまり、二重三重にも中心・周辺・亜周辺構造が入子構造の如くに形成されているということである*8。
■ システム論と帝国主義論
帝国主義論についての崎山さんの議論を紹介した時、何故レーニンの帝国主義論には植民地のことが詳しく論じられていないのかという疑問を提供してきた。この疑問は、レーニンの帝国主義論それ自体が何を論議しているのかということと関連している。そしてそれは百年前の20世紀初頭における資本主義経済の世界的構造がどうであったのかということを論じなければ明らかにならない。
レーニンが「資本主義の最高の段階」として規定した帝国主義とはどういうものなのか?有名な五つの指標をおさらいしておこう。? 生産と資本の集積による独占体の形成、? 銀行資本と産業資本の癒合による「金融資本の寡頭制」の形成、? 資本輸出が「重要な意義」を果たすようになったこと、? 資本家の国際的独占体による世界の分割、? 帝国主義による世界の領土的分割の完了である。この五つの指標の中で植民地経済に関係するものとしては?と?と?が考えられる。しかし、これまでも多く語られてきた植民地諸国からの資源の収奪ということについては指標の中に入っていない。ということは、レーニンがそのことを論じていないわけではないので、この問題については?と?の中に含められていると考えていいだろう。つまり、資本主義経済にとって必須であるはずの植民地支配・収奪は資本の地球の分割と帝国主義の領土的分割という二つの規定の中に当然のこととして入れ込まれていると思われる。そこで注目していただきたいのは、資本の分割と国家の分割とを弁別しているということである。ここに20世紀初頭の帝国主義論を巡る分析と規定が大きく関わってくると見ていいのだろう。つまり、カウツキーの「超帝国主義論」とヒルファーディングの「金融資本論」である。前者は帝国主義の進歩性の問題と後者の段階ではなく政策であるという規定問題である。レーニンが慎重に資本と国家を区別したのは、この議論を踏まえて資本主義の新しい段階としての帝国主義を捉えたと思われる。
では、既に二つの帝国主義世界戦争を知っている我々から見て、このレーニンの帝国主義論はどのような課題を抱えていたのか、考えなければならない。二つの大戦の後にマルクス主義陣営での帝国主義論は「国家独占資本主義論」として一世を風靡したが、レーニンの?の観点である資本家の国際的独占体による世界の分割という観点についてはあまり語られてこなかった。それは、戦争によって資本家の国際的独占体が国家の利害によって分断されたという認識であったように見受けられる。しかし、戦後の歴史を振り返ってみれば、必ずしもそうとは言えないのではないかと私は考える。何故なら、戦後復興の過程でかつての敗戦国の資本家たちは戦勝国の資本家たちからの援助ですくすくと成長したではないかということである。敗戦国の政治形態に関しては著しい変革を強いられたが、資本家の復興は一旦の独占資本の解体を指令したものの、金融資本を中心とした資本の再生は遅滞なく行われたと考えていいだろう。それは冷戦体制による米帝の路線転換が原因であるという見方があることは承知するが、むしろ戦後のIMF/GATT体制の形成の方が先行したことを見るなら、この「国際的資本家団体の世界の分割」という構造そのものは内部の資本相互の競争と葛藤を含みつつも微塵も揺るぎないものであったと言えるのである。
このように考えてみると、国際的な資本家団体の世界分割と戦後の国民国家樹立を目指した民族解放運動とは真っ向から対立する構図として見えてくる。第一次大戦後から始まり、第二次大戦後に一気に広がった第三世界の民族独立運動は国際的な資本家たちにとって脅威となる事態であったと考えるのが妥当だろう。全世界的に広がった戦後の局地戦争はこのことを如実に証明している。では、レーニンの帝国主義論とこれらの事態とに整合性があるのだろうか。レーニンは別の論文で次のように述べている。
「ドイツの『スパルタクス団』は、1915年にドイツ語で刊行された同団の『テーゼ』の中で、帝国主義時代には民族戦争はありえないという主張を掲げた。これは、明らかに間違った主張である。なぜなら、帝国主義は民族的抑圧を激しくするが、その結果、民族的蜂起と民族戦争は(蜂起と戦争を区別しようとする試みは、難破せざるをえないだろう)、単に可能なこと、ありそうなことというだけでなく、まさに不可避的なことになるからである。」(『党綱領の改正によせて』全集26巻P.156)
「帝国主義の時代には、植民地と半植民地による民族戦争は、ありそうなばかりか、不可避でもある。」(『ユニウスの小冊子について』全集22巻p.359)
つまり、レーニンは帝国主義が民族的抑圧を必然とするから民族戦争もまた不可避であるとしている。これは資本主義の最高段階としての帝国主義が何故民族的抑圧を必要としているのかという疑問に対して、「国際的資本家団体の世界の分割」と「資本主義的最強国による地球の領土的分割」を対置していることになる。システム論で言うところの「周辺が必然である」というブルジョアジーの言い分をプロレタリアートの側から見ると、それは「世界の分割」なのである。この二つの分割が戦後世界階級闘争の過程において、後者の「領土的分割」の野望を世界の被抑圧民族の戦いが打ち砕いたということなのだ。しかし、前者の「分割」は依然として打ち砕かれていないというのもまた事実である。
では、この戦後的な帝国主義的資本体制に対して未だ従属的資本主義経済下にある諸国の民衆はどのような革命戦略が可能なのか。再度、レーニンを参照してみる。
「…この戦争が強盗的、奴隷所有者的、反動的な性格のものであるから、またこの戦争に対して社会主義のための内乱を対置する(またこの戦争を内乱に転化しようと努力する)ことが可能であり、必要であるから、プロレタリアートはこの帝国主義戦争で祖国を擁護することに反対するということである。」(『ユニウスの小冊子について』p.363)
ここでもまた先に掲げた表現が繰り返されている。つまり、「奴隷所有者的」とは旧ロシア帝国の統治体制のことであり、いわゆる先進資本主義の民主主義的なそれではないということは明らかである。しかし、レーニンはここで05年革命とは違う戦略を提示している。それは、帝政ロシアに対して「社会主義的内乱」を対置しているということである。ここでも二つの条件を置いていることに注目したい。つまり可能条件と必要条件である。帝国主義間戦争において自国政府における革命戦略が問われるとき、必要であるとはどういうことなのか。この第一次大戦時における帝政ロシアにおける社会主義革命の可能性とは英米をはじめとする先進資本主義国の参戦による先進国プロレタリアートの社会主義革命の課題と連動するということ以外には考えられない。つまり、先進諸国のプロレタリアートが自国敗北主義を掲げて社会主義的内乱を提示するなら、参戦国としての帝政ロシアにおけるプロレタリアートが自国の封建的奴隷所有的な統治体制に対する民主主義革命を対置することは世界プロレタリア革命に寄与できないと考えていたからであろうと思われる。しかしながら、それでもまだ可能条件が残っている。情勢がプロレタリア革命の必要を求めているとはいえ、少なくともそれを可能にする条件があるのか否かは問わなければならないと戒めているのである。
さてここから本題である。戦後的世界資本体制下にあって帝国主義諸国家の「地球の領土的分割」が不可能になった段階における帝国主義間戦争は果たして起こる可能性があるのか否かという問いと、その可否による戦後的民族独立国家における革命戦略はいかにあるべきかという問いが瞬時に浮かび上がり、それに応えることが現下の情勢に相応しい解答となるということである。しかしこれはレーニン帝国主義論の文脈に沿った議論であるということは踏まえておいて欲しい。マルクス=レーニン主義的文脈から言えば、領土的独立を果たしたにも関わらず未だに世界的資本家団体の支配下に置かれ、その隷属下にあって資本主義的国民経済発展の典型的な道筋を実現できていない多くの戦後的独立国家におけるプロレタリアートの政治革命の課題はやはり民主主義革命である。
しかしこの結論にはいくつかの疑問が残る。一つは先に挙げたシステム論で言うところの「資本主義は周辺を必要とする」というテーゼから来る疑問である。なぜなら、戦後的独立国家が典型的な発展を実現することはこのテーゼからは不可能だからである。そして健全な典型的発展においてこそブルジョアジーが形成され、民主主義革命が成就できるからである。そうなると、民族解放・国民国家独立闘争はレーニンが提起した帝国主義間戦争下における先進国プロレタリアートの社会主義革命に連帯した、いわゆる「民族解放・社会主義革命」なのだろうか。先進国プロレタリアートが未だに準備もできていない現下の情勢からは、どう考えてもこれは可能ではない。
システム論においても、帝国主義論においても、現下の情勢を説得的に説明できる理論としては不十分であると言わざるをえないのである。
■ 現下の二つの戦争の歴史的意味について考える
今般、ウクライナへのロシアの侵攻に関して左派が統一した戦争観を持てずに、分裂した状態にあることは、それだけこの戦争の意味が複雑であるという証である。このことはソ連崩壊以降の世界に対する視点が定まらないことに起因していると考える。湾岸戦争とイラク戦争、アフガン戦争という明らかに米国の利害が絡む戦争に関しては概ね「反米」で一致していた戦争観も、同時期に生起したバルカン半島やコーカサスを巡る内戦=戦争に関しては明確な立場をとることができたとは言えない。このような資本主義経済圏の周辺で起こる戦争に関しては、アメリカ、ロシア、中国などの大国が絡む明確な意図を持った戦争、それが資源であれイデオロギーであれ何らかの帝国主義的な利害が絡むものとは異なる特異な戦争が90年代以降頻発していることをどのように見るかが問われる。
ウクライナへのロシアの軍事侵攻がなぜこれほど見解が分裂するのかということを考えるに、それは二つの要素が絡み合っているからだ。一つはロシアのソ連時代から引きずる特異なプーチン的イデオロギーに基づく地勢観が帝国主義的政治に転化したという側面である*9。もう一つは欧米連合におけるNATO的帝国主義政治がロシアとぶつかりあう接点としてのウクライナあるいはコーカサスということになるだろう。この二つの要因は欧米を中心とする国際的資本家団体の世界支配構造に亀裂が入っているということでもある。
単純に発想すれば、NATOとロシア帝国がぶつかり合っているように見えるウクライナ戦争であるが、戦争初期にはNATOの盟主であるドイツの武器支援は慎重であった。これはドイツのロシア産ガスへの依存という国際資本家団体の利害が絡んでいたことは確かである。これを決定的な分裂へ導いたのは英米帝国主義者たちである。とりわけアメリカ帝国主義は中国を念頭に勃興しつつある周辺諸国の資本主義的発展に対して、軍事的な制裁を武器に従来の経済的従属という位置に固定したいとする願望の表れであり、かつ彼らの世界戦略でもある。しかし23年にハマースがイスラエルに攻撃を開始したことによるイスラエルによるガザ・ジェノサイドは事態をより複雑にすることになった。なぜなら、ウクライナにおける戦争が権威主義国家ロシアによる領土的帝国主義であることを名分にするなら、イスラエルのガザジェノサイドはイスラエルの国民国家としての民主制に疑義が浮かび上がるからである。それは旧第三世界の諸国のほとんどが反イスラエルで一致していることから自明であろう。英米帝国主義者たちは自らの植民資本主義精神の発露としてイスラム圏におけるイスラエルの防衛は生命線であるが故に、この矛盾を早期に収束しなければならないはずである。しかし、ウクライナの民族独立運動がそれを許さないというジレンマに陥ることで、国内政治における分裂を招来することになった。今後、トランプの登場によってウクライナ戦争への介入によって停戦協議が始まるとしたら、一挙にパレスチナ問題への強行的解決へ向けて軍事的行動を起こすことが予想される。
これらの予想を含めて、想定できる構図はもはや「国民国家」形成における典型的発展が隘路に陥っており、先進国においても、発展途上国においても「国民国家」における典型的な民主主義的発展、すなわち健全なブルジョアジーの形成が阻害されるということを意味している。レーニンが17年革命において「労農同盟」政府が急速に「労働者政府」へと転化すると想定したのは帝国主義諸国の腐敗とその植民資本主義的な侵略が19世紀的なブルジョアジーの民主主義的発展を歴史的に押し潰したと見たからではないのだろうか。それはしかし20世紀初頭の世界史的な歴史的転換点にあって、民族解放国民国家形成と労農同盟から強行的社会主義革命へと導く戦略に資本主義的発展という法則的な原則を無視した極めて政治的な判断であって、展望のあるものではなかった。つまり、レーニンの後を継いだスターリンの任務が「社会主義政府」の民主主義的任務という従来からの理論とは矛盾した戦略を理解することができなかったが故に、恐るべき粛清政治をとらざるをえなかったのである。彼が理解した限界は二段階革命論という継起的な歴史認識という古典的マルクス主義の教科書的理解であって、新たな時代の二重の革命論という複線型歴史認識には至らなかったということである。
戦後世界はこの誤った路線の下に「民族解放社会主義革命路線」が世界的な標準となり、東南アジア、中東、アフリカの第三世界における民族解放闘争が闘われたことで、極めて困難な敗北を決定づけられた闘争として現在にまで至ったのである。ところが、ソ連崩壊以降の第三世界はそれ以前から始まっていたグローバルサプライチェーンの形成による急速な経済成長と段階革命論の呪縛からの解放によって資本主義的周辺諸国の自立運動が新たな帝国主義的植民地主義の標的となり、その最先端の現れとしてウクライナ・コーカサス、中東レヴァント地方、バルカン地方といった政治的に脆弱な国々を標的とした紛争・闘争が立ち現れてきたというのが今日の状況である。そして今後想定される紛争の拡大はアフリカ諸国へと広がる可能性を孕んでいる。
■ 21世紀の革命戦略はどうあるべきか
百年前のレーニンの労農同盟や二段階革命論は、世界がまだ広大でぼんやりとしたものであることを前提とした理論であった。世界が資本家団体と帝国主義国家によって分割されたとしても、抑圧された多くの民族が反乱し、また帝国主義諸国内の労働者階級が社会主義を目指して闘っているのだから、両者の結合によって世界に革命の嵐をもたらすのは時間の問題であると考えられていた。
しかし、問題は二段階と労農という二つの階級の結合は考えられていたほどには容易なことではなかった。なぜなら、これらの二つの理論には複雑な解決されなければならない諸問題をはらんでいたからである。既に述べたように、二段階という一つの流れの中で民主主義革命から社会主義革命とへ発展する指標はどこにあるのかという疑義が生まれるからであった。毛沢東が失敗したのはこの点であったことは明らかである。また、労農という二つの階級を結合して民主主義革命を社会主義労農政府が実施するという困難な任務に失敗したのがスターリンであった。ここにある失敗の事例を見ると、この問題の複雑な教訓が見えてくる。
現在の旧第三世界における資本主義的発展を見るなら、中国における原始蓄積期における農民工の問題、インドにおける原始蓄積期における被差別階級の存在、南アフリカにおける旧黒人労働者の地位等々、BRICSと呼ばれる発展途上国における疎外された発展形態を見るなら、いずれも国内に周辺を形成することで発展していることが一目瞭然である。ということは、百数十にのぼる世界の発展途上国における資本主義的発展とその下で民主主義的改革を実現するブルジョアジーの形成はほとんど期待できないばかりか、不可能とさえ言えるのではないか。
つまり、二段階という継起性や労農という階級結合などは21世紀における革命理論には不十分であると言わざるをえない。民主主義的改革はブルジョアジーが担わなければならないわけではなく、また社会主義革命が労働者階級だけが担うものでもないということは明らかである。このような硬直的な理論は廃棄すべきである。そして、これまで論じられてきた民主主義革命、社会主義革命、労働者階級、農民階級などの固定的な概念に縛られない二重で一個の革命をこそ追求すべきであるだろう。
更に、問題とすべきはウクライナ戦争、レバント地方における複数の戦争が示す困難な問題は「国民国家」という近代近世におけるブルジョアジーが示してきた土地に縛り付ける領域政治が限界に達していることを示しており、同時にその限界をブルジョアジー自身が入植と国家連合という形態でかつての帝国主義的侵略の新たなバージョンとして実行しつつあるということである。これに対抗するためには革命派自身が国家と古い理論から脱皮しなければならないことは言うまでもないが、かつてのロシアと中国の失敗から学ぶなら、国境を跨ぐ連帯と階級を跨ぐ連帯、民主主義と社会主義を跨ぐ結合と分離こそが求められているのではないか。
この立場に立つなら、あの旧理論に付随する「プロレタリア独裁」という概念が間違っていたということが明らかになる。この概念には国家が必須の条件となる。独裁とは行政権=軍事を用いたものであり、かつての赤軍派が失敗したように、パレスチナと北朝鮮と日本とを結びつけても何ものをも作りえないということは明らかだったことから、軍事に依存する国民国家形成の歴史から速やかに脱却することが重要である。つまり、共産主義を目指す者にとって今や軍事権力を用いた階級抑圧は過去のものとなったと理解すべきである。なぜなら、21世紀の軍事は核兵器なしには成立しないからであり、ブルジョアジーがそれを弄ぶ以上、その愚を踏襲すべきではないからである。
20世紀末から世界中で民族的抵抗運動に小火器を用いた戦術が注目を集めてきた。帝国の軍事もそれに対応して低強度軍事戦略がもてはやされてきたが、この局地的な戦術から「国民国家」を展望することは困難であるばかりか、実現すべき政治そのものさえ不分明で、かつ現実的には宗教的な色彩を濃厚に帯びることになっている。アルカイダのような国境を超えた抵抗運動が宗教性を帯びざるをえないのは、20世紀における社会主義運動の敗北の結果、実現すべき社会像が消失した結果である*10。本論考を終える際にシリアのバアス党アサド政権が崩壊したというニュースが入ってきた。これこそ、まさに「国民国家」形成における第三世界の困難と不可能性を象徴する出来事であると考える。
以上、多くの言葉を用いて過去の理論からの脱却を模索してきたが、私にとってはこれは必須の作業であった。古い理論とはいえ、これまで多くの呪縛を抱えてきたことから、そこからの脱却はまだまだ十分とはいえないものである。あるいは、現在の若い人からは当然と映ることを語っているのかもしれないが、これらは嘗て一時代を栄光に包んだ理論であり、ここからしか新しいものは生まれはしないという信念から認めたものである。
脚注
*1 一部の論者には、この法則が戦後の日本経済の成長には当てはまらないということを主張する者もいる。戦後日本には植民地がなかったからという理由からだ。しかし、これは戦後の経済成長が朝鮮戦争とベトナム戦争という特需に支えられていたという側面を捨象している論議だろう。
*2 ここでは政治的な民族運動ではなく、経済的な民族資本の側面から論じている。
*3 欧米帝国主義とBRICs諸国との角逐として現代世界を捉えているのが、的場昭弘『21世紀世界史講座』(2024年)である。
*4 レーニンは『二つの戦術』で強調したのは労農政府の上からの改革と下からの運動を結合することだとしたのだが、スターリンはこの上からの改革の意味を彼自身の圧政手法と重ね合わせたのか
*5 とは言うものの、20世紀前半の二つの世界大戦は欧州における領土的争奪戦が繰り返されたことから見て、レーニンが想定した欧州先進共和国が領土的野心を失っていたわけではない。
*6 第一次長州征伐(1864年)から西南戦争(1877年)に至る過程全体が幕藩体制解体のための戦争だった。
*7 ナポレオンが北アフリカとレバント地方へ侵略していったのは、明治政府軍が沖縄と蝦夷へ支配を伸ばしたのと相似形であるように見える。
*8 日本における労働構成が正規・非正規によって二分されているのもまたこの中心・周辺構造であるするシステム論的把握が主流である。かつて国境外部に形成された周辺領域が国境内部に侵食してきたのである。
*9 ロシアの階級的な性格については見解が分かれている。帝国主義と見る見解と権威主義国家と見る見方、そして特異なプーチン的イデオロギーの旧帝国的な国家と見る見方が併存している。今回は最も無難な権威主義国家という見方をとりあえずは取ることにした。
*10 アルカイダ等の90年代以降の抵抗運動はその独特のイデオロギーを除いたら、21世紀の抵抗運動のある種の傾向と特徴を帯びていると見られる。この運動に関してはもう一度詳細に分析する価値があると考える。